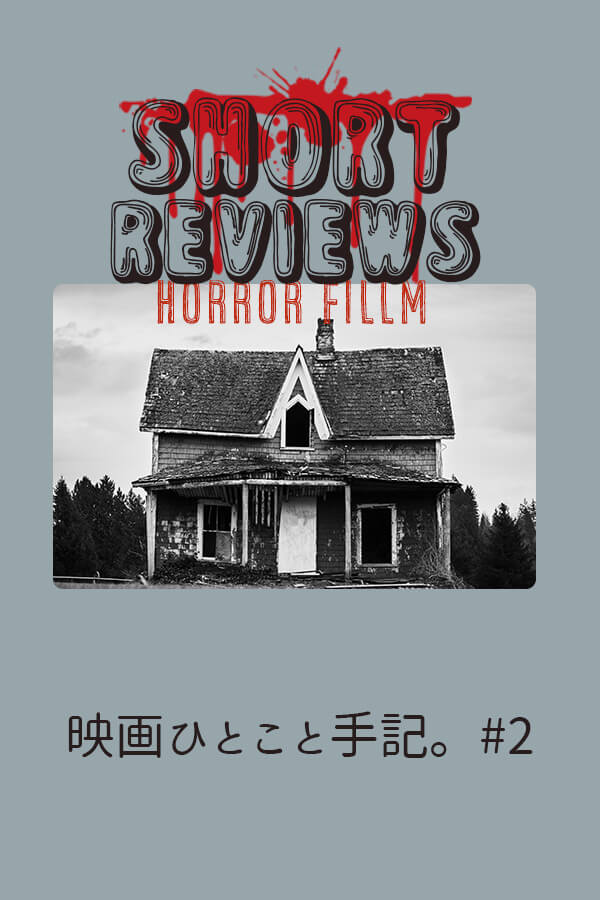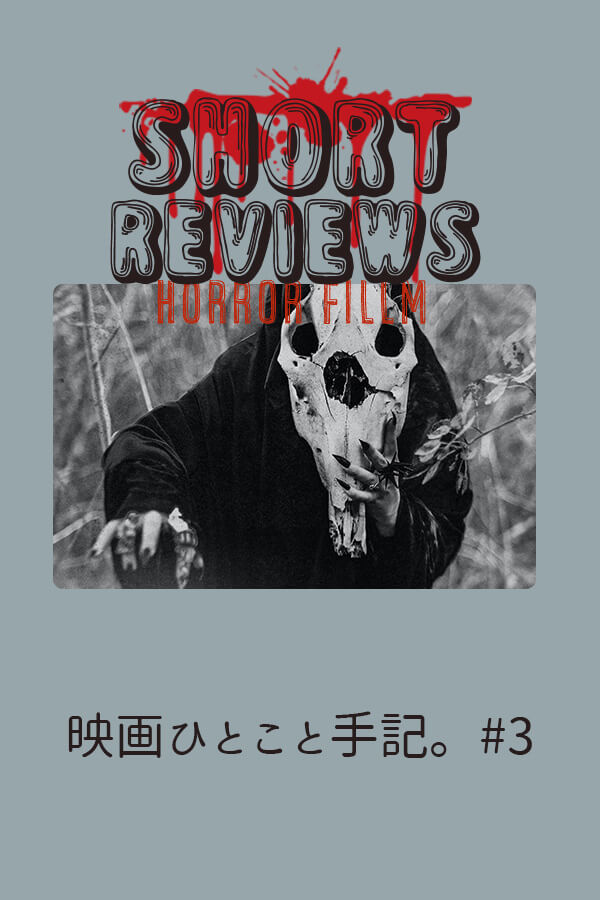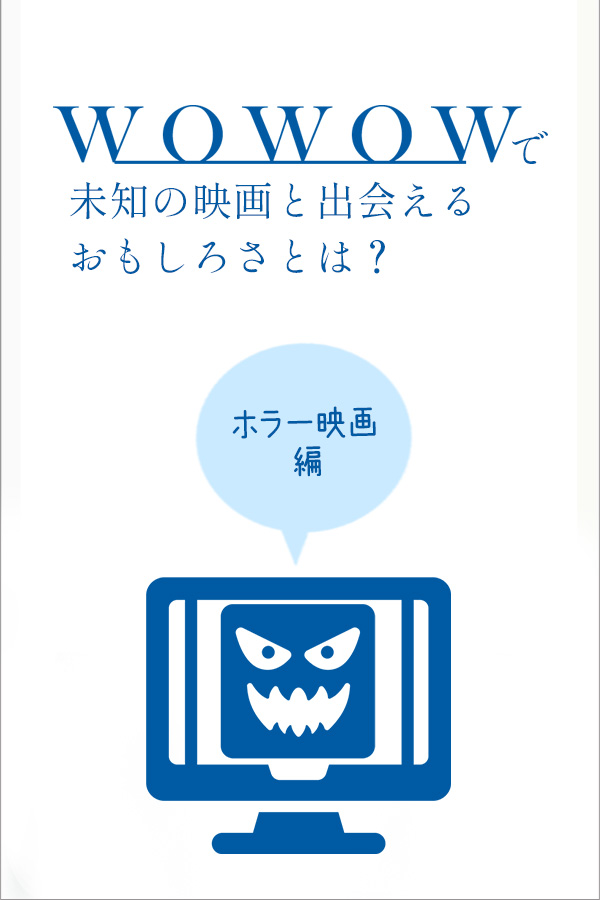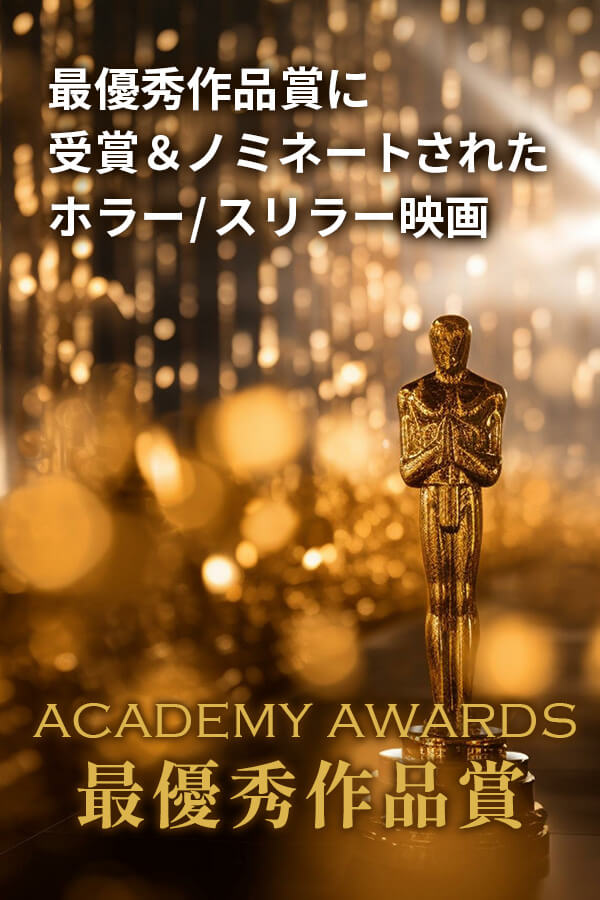【2023.3.11追加】ホラー映画の解説によく出てくるホラー用語辞典
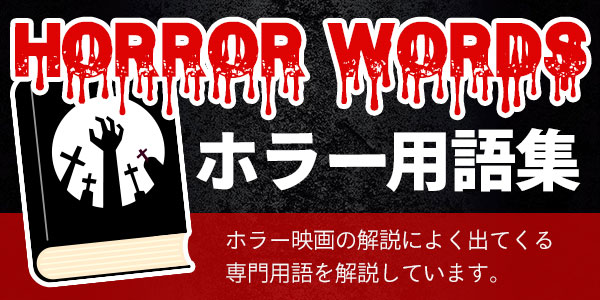
この記事では、ホラー映画や小説の解説を見たりしてると「どういう意味?」みたいな専門用語について自分用に作ってる辞書です。絶賛編集中なので随時更新中。
当ページの説明は、aoringoの備忘録的なものであり、各文献等を参考にはしていますが個人的見解も含んでるのであらかじめご了承くださいませ。
あ行
アートハウス・ホラー -arthouse horror
2010年代に生まれたホラー映画のサブジャンル。日本のミニシアターで上映されるような芸術性と作家性が高いホラー作品のこと。
インディペンデント映画
大手製作会社ではなく小さなスタジオで製作される映画のことで、インディペンデントならではの独創性、前衛的なスタイルの作品が多い。
エクソシスト -exorcist
悪魔祓いの祈祷師。キリスト教、特にカトリック教会の用語で、エクソシスムを行う人のこと。エクソシスムとは「誓い」「厳命」を意味するギリシャ語であり、悪魔にとりつかれた人から、悪魔を追い出して正常な状態に戻すことをいう。
SFホラー -sf horror
『SF的な存在・現象』を中心にしたホラー作品、もしくは『ホラー的な展開・演出』を中心にしたSF作品の事。 どのような存在・現象を『SF的』と呼ぶか、どのような展開・演出を『ホラー的』と呼ぶかは解釈の分かれるところであり、『SFホラー』の定義もまた厳密なものはない。
当ブログでSFホラーは未確認生物や宇宙人以外にも科学的なアプローチのある作品をこちらに個人的な判断でジャンル分けしています。

A24
2012年にスタートしたアメリカの新興インディペンデント系映画製作・配給会社。アカデミー作品賞を受賞した『ムーンライト』、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』などでも有名。
エピック・ピクチャーズ
映画製作・配給などをするアメリカの会社。2017年にはホラーサイト「ドレッド セントラル」を買収し、独自のホラーレーベル「ドレッド」そしてAVODチャンネル「ドレッドTV」を立ち上げました。
オカルト -occult
秘学・神秘(的なこと)・超自然的なもの。ホラーでは、超常現象、幽霊、悪魔など科学的でない現象を題材にした作品に用いられる。
オムニバス -omnibus
いくつかの独立したストーリーを並べて、全体で一つの作品にしたものをオムニバス作品という。
か行
グラン・ギニョール -Grand-Guignol
パリのピガール地区にあった劇場で、1897年の開館から1962年の閉館までホラー作品を中心にしていました。その名前はエリザベス朝やジャコビアン朝の演劇から現在のスプラッター映画まで、生々しくて不道徳なホラー娯楽作品の総称としてよく使われています。
グロ・グロテスク -grotesque
グロ…日本語におけるグロテスクの略語。ロマン主義の時代にグロテスクという言葉が文学にも使われるようになり、次第に「奇怪な」や「異様な」「不気味な」という意味に転じた。現代の日本では、「残虐的な」や「生理的嫌悪感を発生させるものを指す言葉」という元来の意味とは異なった認識が広まった。特に、「グロ」「グロい」と表現される際は、後者の意味で用いられることが多い。
ゴア -Gore
血糊や流血など、べっとりとした血液を表現する言葉。ここから転じて血しぶきが飛び散る残虐シーン等のある作品。
さ行
サイコパス -psychopath
精神障害の一種であり、社会に適応することが難しい恒常的なパーソナリティ障害、または精神病と健常との中間状態の精神病質を持つ者のこと。
サイコホラー-Psychological horror
サイコロジカルホラーの略。精神的、感情的および心理的状態に起因する恐怖により読者、視聴者、またはプレイヤーを脅かす、妨害する、または不安定にするホラー・フィクションのサブジャンル。しばしば、サイコロジカルスリラーと重複し、設定やプロットのサスペンス、ドラマ、アクション、ホラーを高め、不気味な感覚を提供するために、不安定で信頼できない、悲惨な状況を表現している。
サスペンス -suspense
ある状況に対して不安や緊張を抱いた不安定な心理、またそのような心理状態が続く様を描いた作品をいう。より広い意味においては、観客や読者が作品(の行く末や登場人物など)に対して不安や緊張の心理、物語の結末を知る事への希求を抱かせ、その作品に対しての興味と関心を持続させる事ができる(あるいは、製作者がそのように意図した)作品もサスペンスといわれる事が多い。
当ブログでは、超常現象をオカルトに分類するのに対し、サスペンスは現実的な恐怖つまり事件もの、とくに警察・刑事が登場したり捜査などする作品はサスペンスに分類しています。

シチュエーションスリラー -situation thriller
物語の状況設定を極端に限定することで緊迫感を高める手法で製作されたホラー映画のサブジャンル。逃げ場のないデスゲーム系ホラーなどは多くこのジャンルに分類されていることが多い。
ジャッロ -Giallo
「ジャッロ」とは60年代イタリアに生まれたスリラー文学、映画ジャンルのことで、主に主題は殺人である。
ジュブナイルホラー -Juvenile horror
少年期を題材にした映画でかつ、少年から大人へと成長していく物語にホラー要素が含まれているもの。
スラッシャー -slasher
切り裂き魔を意味する英単語。「スラッシャー」という用語は人殺しを含むホラー映画全体を指して使用されることがあるが、映画批評家はスラッシャー映画を、スプラッターやサイコロジカルホラーなどとは一線を画す特徴をもつ一つのサブジャンルであるとみなしている。
スラッシャー映画の定義は、”過去の過ちがその記念日にひどいトラウマとして呼び起こされ、それが殺人鬼を刺激して殺人に駆り立てる、というお決まりの構造をもつ”らしいです。

スリラー -thriller
テンポが速く、アクションの要素が高頻度に出ることが特徴であり、ホラー作品においては、観客(読者)に作品ストーリーそのもの、またはシチュエーションによって「緊張」や「不安」をもたせる。
ゾンビ -Zombie
何らかの力で死体のまま蘇った人間の総称である。多くはホラーやファンタジー作品などに登場し、「腐った死体が歩き回る」という描写が多くなされる架空の存在である。
た行
ダーク・キャッスル・エンターテインメント -Dark Castle Entertainment
映画監督ロバート・ゼメキスとジョエル・シルバーが共同で設立したホラー映画専門の製作会社。もともと1950年代から1960年代に仕掛け満載のB級映画で名声を博したマニア人気の高いホラー映画作家、ウィリアム・キャッスルの作品リメイクのために設立された。現在ではオリジナル企画も手がけている。
テラー -Terror
現実の出来事から直接的に感じる恐怖。特に身がすくむような強い危険を感じさせる出来事から受ける恐怖を表す。またそのような恐怖を与える事態や人などに対しても使われる。
- 恐怖
- テロ(行為)
- 〔行儀の悪い子どもなどの〕やんちゃな人、手に負えない存在、厄介者
トーキー -Talkie
映像と音声が同期した映画のこと。サイレント映画(無声映画)の対義語として「トーキー映画」と呼ばれることもある。
トーチャーポルノ -torture Porn
トーチャー(拷問)+ポルノ(性的興奮を呼ぶもの)の造語。フィクション作品では、残酷描写に興奮する人間が描かれているものをこう呼ぶことがある。
な行
ネイチャーホラー -Nature Horror
「ナチュラルホラー」とも呼ばれる。自然の力、とくに動物や植物などが登場人物に脅威を与えるような内容のホラー映画のサブジャンル。しばしば「アニマルパニック」と重複する。厳密な定義はないようで、直接的に生き物が襲ってくるものではなく、森や海など、本来なら心安らぐ場所である自然のシチュエーションにおいて恐怖の展開がある作品の場合も、ネイチャーホラーと呼ばれる場合がある。
は行
P.O.V
「point of view(ポイント・オブ・ビュー)」の略で「ピーオーブイ」と読む。映像や撮影の領域では「一人称視点」で撮影する「主観ショット」「視点撮影」のことを指すことが多い。カメラの視線と登場人物の視線が一致した撮影手法のこと。自分で撮影したカメラ視点によるホラー映画をPOVホラーなどという。
ファウンド・フッテージ -Found footage
映画(やテレビ番組)のジャンルの1つでモキュメンタリーの一種。撮影者が行方不明などになったため、埋もれていた映像という設定のフィクション作品。撮影者と無関係な者の手に渡り、そのまま公開されることになったという設定でもある。第三者によって発見された (found) 未編集の映像 (footage)が語源。
フェアー -Fear
「恐怖」という意味の最も一般的な語。「恐怖」という意味の最も一般的な語で、恐怖や未来に対する不安、心配などについての幅広い感情を表す。危険や苦痛、脅迫などの恐れを感じさせる状況から受ける、人の感情を示す。
- 恐れ、恐怖感、恐怖心◆不可算
- 懸念、心配(事)、不安
- 〔神への強い〕敬い、崇敬
- 恐ろしいもの、心配の種
ブラムハウス・プロダクションズ -Blumhouse productions
アメリカの映画/ドラマプロデューサーのジェイソン・ブラムによって設立された制作プロダクション。主にホラー映画の制作で知られており、少ない予算で映画を制作し、監督に創造的な自由を与える独自性で近年ヒット作を多く輩出していることで注目されている。
ホーム・インベージョン -home invasion
invation…「侵入」の意。自宅に何者かが侵入してハプニング・恐怖を描く作品を「ホーム・インベージョン映画」と呼ぶ。自宅が呪われていたり家族が悪魔に憑かれたりなどして怪奇現象が起こるホラー作品を「ハウスホラー」と呼ぶことがあるのに対し、こちらは非現実的ではない”人間”による恐怖をさす場合が多いらしい。
ホラー -Horror
嫌悪感を伴うゾッとするような恐怖。恐ろしい光景を見たり、そのような状況を想像したときに感じられる、抽象的な「恐怖感」を表す。「身の毛もよだつ、ぞっとするような恐怖」というニュアンス。ホラー映画とは、恐怖や嫌な気持ちを感じる作品をまとめてそう呼ぶ。
1) 恐怖、恐ろしさ、恐ろしい人、物、事。(terrorとは違い嫌悪感を伴う)
2) 1)から転じて、心霊や怪物、嫌悪感を伴う恐怖を扱った「ホラーもの」「ホラー作品」のこと。
3) 憎悪、嫌悪。
4) ぞっとする気持ち。ふさぎ込み。
ま行
マンブルコア -mumblecore
アメリカのインディペンデント映画(自主製作映画)の一種で、多くは若い白人中産階級の日常生活や人間関係を主題とし、きわめて低予算で製作される点が特徴。あえてエピソードの羅列にとどめ明確な物語構造を持っていないことも多いが、2000年代のアメリカ社会の新しい現実を描いているとして注目されるようになった。「マンブル mumble」は「低く不明瞭に発音する・もぐもぐ言う」を意味する言葉で、作品に登場する若者たちがしばしば不明瞭な発音で早口に英語の台詞を口にするためこの呼び名がある。
ミステリー -mystery
フィクションジャンルとしては基本的に推理もののことであり、作品中で何らかの謎が提示されやがてそれが解かれてゆく、という類のもの。
モキュメンタリー
映画やテレビ番組のジャンルの1つで、フィクションをドキュメンタリー映像のように見せかけて演出する表現手法。擬似を意味する「モック」と「ドキュメンタリー」を合成したかばん語であり、「モックメンタリー」「モック・ドキュメンタリー」ともいう。